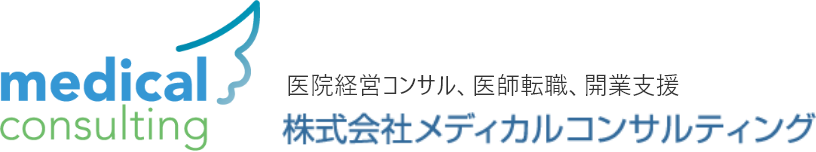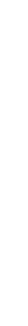医療機関であるクリニックは、単独で存在しているわけではありません。地域にあるほかの医療機関とも連携していますし、薬局とも深い関わりがあります。また、介護機関との連携も重要です。
ここでは、地域医療・地域介護の担い手のひとつであるクリニックが、介護機関との連携をはかる意味やその方法について解説していきます。
国は、介護機関と医療機関の連携を後押ししている
介護機関の利用を必要とする人たち(特にご高齢の方々)は、医療ケアも必要としていることが多いといえます。そのため、その人たちが暮らしやすくするためには、介護機関と医療機関の連携が欠かせません。医療機関と介護機関が、相互に情報を提供し合うことが重要になるわけです。
このようなことから、国も介護機関と医療機関の連携を推奨しています。今から15年ほど前の2009年には、医療機関との連携を指標のひとつとして介護報酬の加算が行われるようになりましたし、直近の2024年にはさらに制度が強化・新設されるようになりました。
また、患者様が医療機関を退院するときには、その医療機関が作成したリハビリテーション計画書を、リハビリテーションを受け持つ施設が受け取ることも義務化されました。これは、質の高いリハビリテーションを、一貫して患者様に届けることを目的としています。さらに、理学療法士などのリハビリテーションを担う職務にある人は、その患者様の退院前に、退院前カンファレンスに参加することが求められるようになりました。
上で挙げたものは一例ではありますが、国は、医療機関と介護機関の連携の強化を目指して、さまざまな施策を打ち出しているといえます。また、今後もこの展開は続いていくものと思われます。
医療機関側にも加算がある

介護機関と医療機関の連携は、介護機関にのみプラスになるものではありません。
協力医療機関として介護機関と連携をはかっている場合、急患が出たときの対応を行うことで、医療機関側にも「介護保険施設等連携往診加算」が加算されます。また、介護機関で介護を受けていた患者様を医療機関が引き受けた場合は、「協力対象施設入所者入院加算」が医療機関側に加えられることとなります。つまり、介護機関と連携して患者様に対応していくことが、医療機関の経営面でもプラスになるということです。
ちなみにこのような措置は、患者様のQOLの上昇や痛みの軽減に寄与するだけではなく、感染症予防の観点からも非常に有用だとされています。
なお、介護施設の協力医療機関となるためには、
・患者様が急変したときに、常時医師もしくは看護師が相談を受け付けられる体制にしておくこと
・介護施設からの要請があったときに、常時診療を行える姿勢にしておくこと
・(病院の場合)患者様の急変があったときには、入院をさせることができる体制を整えておくこと
が条件とされています。
もっとも、これらの条件は、「1つだけの医療機関」で満たす必要はありません。たとえば、「急患の入院を受け入れられる環境にはないが、常時相談が受け付けられる医療機関A」+「常時診療を受けつけられて、入院もさせられる医療機関B」の2つを協力医療機関とすることも可能です。このため、大病院でなくても、在宅療養支援診療所なども、協力医療機関となり得ます。
高齢化が進む日本において、患者様にとっても、介護機関にとっても、医療機関にとっても、「介護機関と医療機関の連携」は非常に重要なものとなっています。これは患者様を支えるためだけのものではなく、医療機関の経営を安定させる支えにもなりうるものです。
私たち株式会社メディカルコンサルティングでは、協力医療機関になるべきかどうかについての助言を受けたい、また協力医療機関になることのメリット・デメリットについて詳しく知りたいなどのご相談を引き受けています。